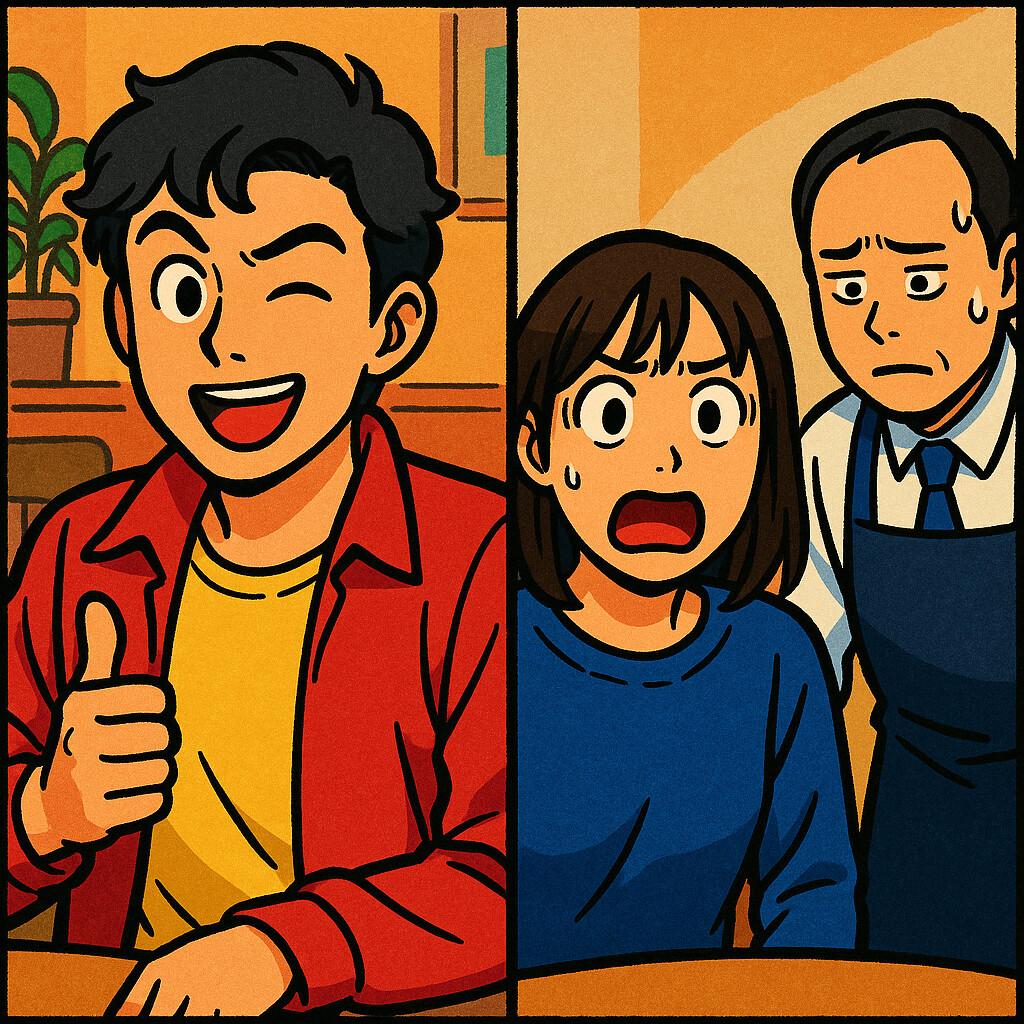
お店の常連だと語る知人
私の知人である健太(けんた)さんは、いつも少し得意げです。
「俺さ、いろんな店に顔が利くんだよね」 それが彼の口癖でした。
ある日の午後、私、美咲(みさき)と健太さんは、彼が「特に行きつけだ」と豪語するカフェを訪れました。
落ち着いた雰囲気の、素敵なお店です。
席に着くなり、彼が私にウインクしてきました。
「この店、常連だから覚えられてるよ」
(ああ、また始まった) 私は内心ため息をつきながら、メニューを開きました。
注文を取りに来たのは、入ったばかりに見える若い店員さんでした。
健太さんは待ってましたとばかりに、わざと大きな声で言います。
「いつもの」
店員さんは「え?」と困惑した顔。
それもそのはず、健太さんは具体的なメニューを何も言っていません。
すると、奥から店長らしき男性、田中(たなか)さんが慌てた様子で出てきました。
常連なんかではなかった…
「健太様! いらっしゃいませ」
(お、本当に覚えられてるんだ) 私が少し感心しかけると、田中さんの次の言葉に空気が凍りました。
「本日は、どのようなご要望でしょうか…? お飲み物の温度や、氷の形など、何かございましたら…」
その表情は、常連客を迎える笑顔ではありません。
明らかに「面倒な客が来た」と警戒している顔です。
健太さんは「いや、今日は普通にブレンドコーヒーでいいよ」と、なぜか急に小さな声になりました。
田中さんは「かしこまりました」と深くお辞儀をして去っていきましたが、その背中からは緊張感が漂っていました。
私はすべてを察しました。
彼が覚えられているのは、優良な「常連客」としてではありません。
何度も細かいクレームをつけ、スタッフさんを困らせてきた「要注意人物」として認識されているのです。
「な? 覚えられてただろ」 健太さんはまだ得意げに私に笑いかけてきます。
私は「そう…ですね」と曖昧に返すしかありませんでした。
彼が喜んでいる「覚えられている」という事実が、こんなにも恥ずかしいことだったなんて。
本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。
※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。
※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。















